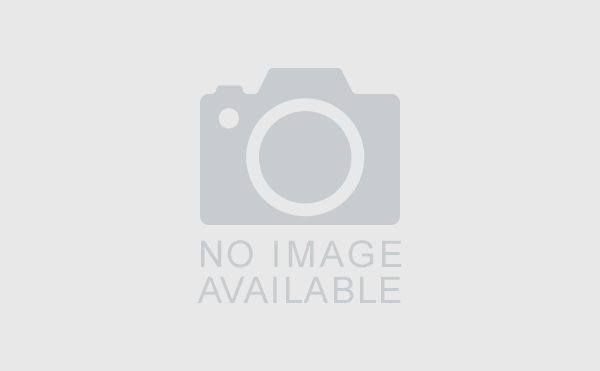偉人クイズ

以下に当てはまる人物は誰でしょう?
1、平安時代中頃に生まれる。本名は伝わっていない
2、父から和歌、漢学を学び賢く育つ。また父と同じようにひょうきんな一面をもつ人物
3、天皇の后に教育係として仕える。主人とはとても気が合い仲は良好だった
4、主人からもらった紙を用いて随筆を書きはじめる
5、宮中ではいろいろな人と交流を持ち、赤染衛門や和泉式部といった女流歌人とも仲がよかった
6、父や曾祖父が歌人として著名で、その名を汚してしまうと歌会には出ないようにしていた
7、主人が亡くなった後の足跡はわかっておらず、落ちぶれてしまったが相変わらず機知に富んでいたという説話がある
8、中古三十六歌仙、女房三十六歌仙に選出されている
9、父は清原元輔、曾祖父は清原深養父と有名な歌人で一緒に百人一首に選ばれている
10、国語の教科書に必ず載っている「春はあけぼの」で始まる『枕草子』の作者
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
清少納言
☆解説
1、この頃の女性の本名はごく親しいものにしか知らされていない。清少納言の清は清原氏から、少納言は由来が不明とされている
2、父の清原元輔は三十六歌仙に選ばれている歌人でひょうきんで人を面白がらせるのを好む人物だったという
3、正暦4年から長和2年(993~1000)の間、中宮定子が亡くなるまで仕えていた
4、定子が一条天皇からもらった紙の冊子を何を書くか訊ねられたときに「枕にしてはいかがでしょう」という返答をしたという。これは唐代の詩人白居易の『白氏文集』にある「書を枕にして眠る」を引用したなどの諸説があるが、その面白い返答から冊子を与えられ、随筆を書くきっかけとなった
5、社交的で負けん気が強く、才気煥発で父親譲りの面白さを兼ね備えており人気だったという
6、定子の催す歌会にも参加せず、それも快く認められていたという
7、200年後の鎌倉時代に編纂された『古事談』の話であり、真偽はいかに
8・9、本人は歌よりも随筆の方を得意としていたようだが、後世にもしっかりと認められている
10、世界最古の随筆文学で日本三大随筆の1つ。解説4のやりとりから『枕草子』と名づけられたとされる。「いとをかし」という言葉が多用されるのでをかし文学ともいわれる
同時代の人ということで何かと紫式部と比較されてけなされることも少なくない清少納言。しかし、じゅくちょーは清少納言の方が断然好きである!
学生時代に「春はあけぼの」の情景に対する感動に共感することが多かったからだ(『源氏物語』にはそこまで思い入れも感動もしなかった、面白いけど)。
性格が悪いとかなんとか言われがちではあるが、中宮定子に対する優しさや愛情を感じる面も多く、辛い境遇にある中を前向きに進んでいこうという強さを感じられるところもよい。
まだ『枕草子』を全部読んでないのでいつか読もうと思って狭間校の本棚にも置いてあるが、その日が来るのはいつだろうか(笑)
遊び感覚で学べて賢くなる「寺子屋コース」は和泉学習研究所狭間校、片倉校で毎週実施中!